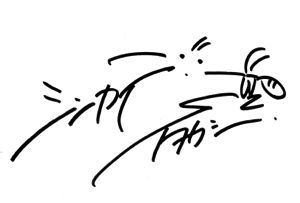夜な夜な、オオカマキリモドキの観察をしている。
夜の熟柿レストランは、昼間より多くの昆虫たちで盛り上がっている。
カメムシ、蛾類がもっとも多い。


夜の熟柿レストランは、昼間より多くの昆虫たちで盛り上がっている。
カメムシ、蛾類がもっとも多い。
ここに通い詰める肉食常連客には、ハラビロカマキリが多く、今夜はウスバカゲロウの一種も来ていた。
そして、もちろんオオカマキリモドキの姿もあった。ただし、数は減った。
一晩に1頭見つけるのがやっと。
高い梢にもいて、おそらく見落としもあるだろう。
オオカマキリモドキの獲物は、小蛾クラスがせいぜいで、あまり大きな頑丈な体の獲物には歯が立たない。
昼間の柿の木に多数のオオカマキリモドキがいたのは、夜の狩りがお目当てであり、その居残り組であったのではないか、と想像する。
ツマグロカマキリモドキ、以外のカマキリモドキの多くは夜行性。
全国的に分布するキカマキリモドキの観察では、夜のクリ林でクリの花に来る昆虫を狩っていた。彼らの出現期は、6月のクリの開花期と重なる。地域や標高によっては違ってくるだろうが、少なくとも多摩丘陵ではそうであった。
そして、昼間、クリ林を歩くと多数のキカマキリモドキを見つけることができた。今回の柿の木のオオカマキリモドキと、良く似ていると感じた。
もっとも、その当時のクリ林は今は開発されて消滅したが。
柿の木の傍の薮では、ねぐらについたクロコノマチョウがいた。止まり方は、タテハモドキと似ている。二頭が並んでいるところも。
今朝は一番で、アブラゼミが鳴いていた。
夜は蚊が多くて、ボコボコに刺されてしまった。昨日、今日と蒸し暑い日が続く。